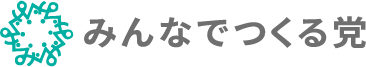声を上げた人が命を落とす社会に、終止符を。-助けを求めた人が必ず守られる社会へ-
インターネットは、思想や経験を共有し、深い絆を生むかけがえのない場です。しかしその一方で、悪意の言葉が矢のように飛び交い、誰かの心や人生を深く傷つける場にもなっています。
繰り返されるネットリンチ、止まない誹謗中傷。
「助けて」と声を上げた人が、制度の壁に阻まれ、絶望の果てに命を絶つ――そんな痛ましい出来事を、私たちはあまりにも多く目にしてきました。 被害者は、スクリーンの向こうにいる“知らない誰か”ではありません。
あなたの友人、職場の同僚、大切な家族、あるいはあなた自身かもしれないのです。
誹謗中傷は、インターネットという「場所」の問題ではなく、私たち一人ひとりが生きる「社会の問題」です。だからこそ、政治が本気で向き合い、解決へと導く責任があると私は確信しています。 私は、誹謗中傷を根絶するために、以下の3つの制度改革を公約として掲げます。
これらは、被害者を守り、加害者に責任を負わせ、言葉の暴力を社会全体で決して許さない仕組みを築くための具体的な一歩です。
1.匿名によるネットリンチを根絶する
――誰もが安全に発言できるインターネットを
匿名性は表現の自由を守る一方で、悪意の隠れ蓑にもなっています。現在のネット空間は、無法地帯ともいえる「治外法権」の状態にあります。
- 身元開示の遅さ:現行制度では、加害者の身元特定に半年以上かかることが多く、証拠(IPログ)は3ヶ月程度で消滅し、被害者は泣き寝入りを強いられます。
- 悪意の拡散速度:1つの投稿が数時間で数万リツイートに及び、被害者の名誉が回復不能になる一方、法的手続きはあまりにも遅い。
- プラットフォームの対応格差:企業ごとの開示協力の姿勢にばらつきがあり、被害者保護の最低基準が欠如しています。
- 開示請求のワンストップ化:裁判所やプラットフォームを介した煩雑な手続きを簡素化し、被害者が迅速に加害者の身元を特定できる仕組みを構築。大規模プラットフォームには、利用者の個人情報登録を義務付けます。
- ログ保存期間の法定延長:事業者に対し、ログの最低保存期間を現行の3ヶ月から1年以上に延長する法整備を推進。
- 事業者の協力義務と罰則:プラットフォームに開示協力の法的義務を課し、違反には厳格な罰則を適用。
これにより、匿名性を悪用した攻撃に歯止めをかけ、被害者の救済を迅速化します。
2.「助けて」の声が必ず届く支援体制
――被害者を孤立させないセーフティネットを
「助けて」と声を上げた人が、制度の壁に阻まれ救われない現実を変えます。被害者を支え、心の傷を癒す時間を確保する仕組みを構築します。
- 警察の縦割り構造:同一の加害者による複数地域での被害が、警察署ごとのバラバラな対応により放置されるケースが頻発。
- 経済的負担:刑事告訴には告訴状作成のための弁護士費用が必要な場合が多く、被害者は高額な負担を強いられます。
- 告訴期限の壁:名誉毀損や侮辱罪の告訴期間は、犯人を知った日から6ヶ月以内。うつやPTSDで動けない間に時効が迫る事例が多発しています。
- 警察の情報連携強化:全国の警察署間で被害情報を一元化するデータベースを構築し、迅速な捜査を可能に。
- 法テラス支援の拡充:経済的負担を軽減するため、法テラスを通じた無料法律相談や弁護士費用の補助を刑事告訴にも拡大。
- 告訴期間の延長と罰則強化:名誉毀損や侮辱罪の告訴期間を1年以上に延長し、加害者への罰則を厳格化。
被害者が孤立せず、確実に支援を受けられる社会を築きます。
3.加害者に「法的リスク」を明確に
――誹謗中傷に高すぎる代償を
「どうせ捕まらない」「安く済む」という加害者の軽い心理が、誹謗中傷をエスカレートさせています。加害者に明確なリスクを突きつけ、再犯を防ぎます。
- 二次被害の連鎖:被害者が訴訟を起こすと、住所流出や反訴による恫喝など新たな被害が生じる。
- 集団加害への対応不足:ネット上の多数の加害者が関わる場合、個別訴訟では対応しきれない。
- 抑止力の欠如:軽い罰則では、加害者の行動を変える効果が薄い。
- 懲罰的損害賠償制度:悪質な誹謗中傷に対し、米国の制度を参考に高額な賠償金を課す仕組みを導入。
- 反SLAPP法の制定:恫喝目的の反訴を阻止し、被害者が恐れずに声を上げられる法律を整備。
- 一括賠償請求システム:集団加害の場合、プラットフォームを通じて一括で賠償請求できる仕組みを構築。
- 民事訴訟時の個人情報保護:訴訟時の住所公開による二次被害を防ぐため、個人情報の閲覧条件を厳格化。
加害者に「言葉の暴力は高くつく」と自覚させ、再発を抑止します。